「せんせい、ちょっと休憩しよ。」に込めた想いと、自己紹介
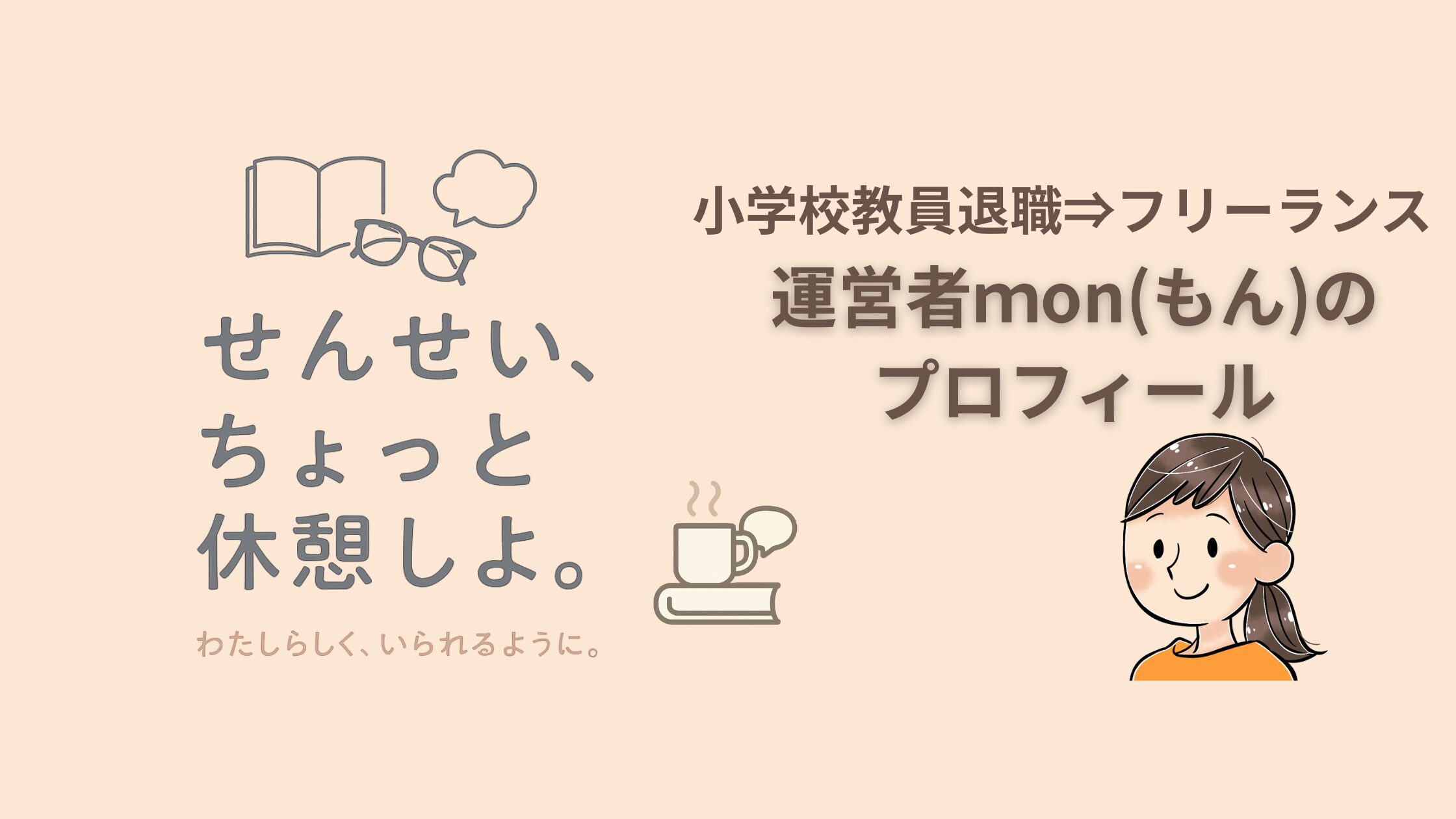
楽しいときもあった教員生活。でも育休から復帰すると
- 朝はバタバタ
- 教材研究の時間がない
- 年休もとりづらい
- 子どもの急な発熱やお休みに対応するのが大変
「もうつらい、一生この生活なのかな…」
同じような育休復帰の教員仲間と話しても、みんな同じ用に悩んでいて、このままでいいのかな…と不安は解決されず、モヤモヤ。
あなたと同じように悩んで苦しんでいました。

はじめまして。
ママ教員向けサイト「せんせい、ちょっと休憩しよ。」を見つけてくださり、ありがとうございます。
管理人のmon(もん)です。
- 家族:夫・2人の子ども(保育園・幼稚園)
- 職業:公立小学校で10年以上勤務。育休明けからモヤモヤを抱えるように
- 教員として好きだったこと・やりがいを感じていたこと:子どもたちの成長、同学年の先生方とこれからについて話し合うこと
このサイトでは、34歳で育休取得後、職場復帰をし、その後退職。フリーランスとして働きだした私の体験談や、教員の働き方について書いていきます。
「育休復帰からが本当の戦いだった」わたしのリアル
- 朝のバタバタ(子どもの準備、自分の出勤、保育園送迎)
- 教室では全力、家では母モード。頭が切り替わらない
- 教材研究ができないことへの焦り、「こんな授業でいいの?」という不安
- 年休の取りづらさ。子どもが熱を出しても休めない現実
- 周囲に頼れず、ひとりで背負ってしまっていたこと
仕事も育児も100%でやりたいのに、できない私
育児休暇から職場に戻った初日。
久しぶりの教室、黒板、子どもたちの笑顔に懐かしさを感じながらも、心のどこかで「これからどうなるんだろう」という不安が大きくなっていきました。
実際に、復帰してからの日々は想像以上に過酷で、「ここからが本当の戦いだった」と思い知らされました。
朝は、目覚ましと同時にスタートダッシュ。
4時ごろから、その日一日の流れが気になり、いまいち深く眠れず。子どもが起きる前に一日の流れを確認し、自分の身支度を済ませる。
6時には眠そうな子どもを起こし、朝ごはんを食べさせ、着替えさせ、保育園の準備をし、急かしながら車に乗せて幼稚園に送る。到着はいつも1番か2番。(1・2位を争う相手もママが教員)
無事に学校(職場)に到着したときには、すでに体力を使い果たしているような感覚でした。
それでも職場に着いた瞬間から“先生モード”に切り替えなければならない。
子どもたちの前ではいつも明るく、元気でいなければいけない。
でも、心の中では「母親スイッチ」がずっと切れないままで、頭も気持ちもなかなか切り替えられない。
そんなギャップに、どんどん自分が擦り減っていくのを感じていました。
さらに辛かったのは、教材研究の時間がまったくとれなかったことです。
子どもたちのために、もっと良い授業をしたいという思いはあるのに、放課後は会議や事務仕事で時間がなく、家に帰っても夕食・お風呂・寝かしつけ。
ようやく寝かしつけたと思ったら、自分もそのまま寝落ちしてしまう。
「準備できていないまま授業に入ってしまった」「今日の授業、あれでよかったのかな…」と、自分を責める気持ちばかりが募っていきました。
また、子どもが急に熱を出してしまったときのこと。
本当は年休を取って付き添いたかったのに、「今日だけは絶対に休めない」と我慢して実母に我が子を任せ、職場に行った自分。
そのときの後ろめたさや申し訳なさは、今でも心に残っています。
学校現場には、「年休は自由に取れる制度ではあっても、実際は空気を読まないといけない」ような空気が確かに存在していました。
周囲に相談できる人がいないわけではありませんでした。
でも、「自分が弱音を吐いたら、みんなに迷惑をかける」「この大変さは、私が選んだ道だから我慢するしかない」
そんなふうに思い込んで、気がつけばすべてを一人で抱え込んでいました。
育休からの復帰は、ただ仕事に戻るということではありません。
「母」と「先生」、2つの役割を同時に全力でこなさなければいけない、終わりのないマラソンのような日々の始まりでした。
「せんせい、ちょっと休憩しよ。」に込めた思い
「転職 教員 子育て」
そう検索してみると、情報はたくさん出てきます。
転職の流れ、向いている仕事、年収の比較…。
もちろん、それらはとても大切な情報です。
でも、当時の私にとっては、それらのどれもがどこか現実味を感じられず、「教員しかしたことない自分はそこまで動けるだろうか」と、逆に落ち込んでしまうこともありました。
「今すぐ辞めたい」というよりも、
「このままでいいのかな」「続けていけるのかな」
そういった、“グラグラしている気持ち”を受け止めてくれる場所が、当時の私には見つかりませんでした。
「がんばってるのに、うまくいかない」
「誰にも相談できない、だけど限界かも」
そんな思いを抱えたまま、走り続けるママ先生たちに、まずは「ちょっと立ち止まっても大丈夫だよ」と声をかけたかった。
それが、このブログのタイトル「せんせい、ちょっと休憩しよ。」に込めた一番の気持ちです。
このブログでは、無理に行動を促すことはしません。
転職をすすめることも、教員を辞めることを押しつけることもしません。
ただ、「がんばってるよね」と、まず今のあなたの状態を認めるところから始めたいんです。
仕事も育児も、どちらも真剣に向き合ってきたからこそ、今の苦しさがある。
手を抜きたくない気持ち、母としても先生としても“ちゃんとしたい”気持ち。
その想いの強さこそ、あなたの誠実さだと私は思っています。
だからこそ、このブログは「自分を責める場所」ではなく、「自分をねぎらう場所」にしたい。
少し休んで、考える時間を持って、それからまた一歩踏み出す。
そのきっかけになるような場所でありたいと願っています。
このブログで伝えたいこと・できること
「教員を辞めるべきか、続けるべきか」
この問いに、正解はありません。
人によって、家庭の事情も、職場環境も、価値観も違うから。
そして何より、心と体の状態も日々変わっていくものです。
だからこそ私は、「こうすればいい」と決めつけるのではなく、
いくつもの選択肢を提示して、「あなたが“自分で選べる”ようになる」ことを、このブログのゴールにしたいと思っています。
たとえば…
・教員を続けながら、自分の時間をつくる工夫
・非常勤や育短勤務など、柔軟な働き方のリアル
・在宅ワークや副業という選択肢
・教員を辞めた後の生活はどうなるのか
・お金の不安への備えや、手当・支援制度の情報
・同じように悩み、乗り越えてきた先輩たちの声
私は、転職エージェントでも、キャリアコンサルタントでもありません。
だからこそ、できるだけ「現場目線」で、「母親としての感情」も大切にしながら、情報を発信していきたいと思っています。
このブログを読んでくれる方が、自分の気持ちに少しずつ気づいて、
「わたしはどうしたいのかな?」と、自分の軸で考えられるようになってほしい。
そして、自分が選んだ道を、自信を持って歩いていけるように――。
そんな願いを込めて、
ブログでは以下のようなテーマを中心に発信していきます:
- 子育てと教員生活のリアルと対策
- 教員ママが考える“自分らしい働き方”とは?
- 転職・副業・非常勤など柔軟な選択肢の情報
- お金と時間の不安を減らすための工夫
- 悩んでいるのはあなただけじゃない、という安心感
どれも、「読んだあとに、少し心が軽くなる」ことを意識して書いていきます。
あなたが立ち止まっている“いま”を、次の一歩につなげるお手伝いができたら。
このブログが、そのきっかけになれば嬉しいです。
読んでくれるあなたへ——わたしからのメッセージ
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
もしかしたら、今このページを開いたあなたも、
「このままでいいのかな」
「限界かもしれない」
そんな気持ちを抱えているのかもしれません。
でも、大丈夫です。
まずはその気持ちを、ちゃんと感じてあげてください。
泣きたい時は泣いていいし、立ち止まりたい時は立ち止まっていいんです。
仕事も、育児も、どちらも大切にしてきたあなた。
その努力は、ちゃんと伝わっているし、誰よりもあなた自身がわかっているはずです。
このブログは、がんばることをやめる場所ではありません。
「がんばりすぎている自分に気づいて、少し休む場所」
「もう一度、自分らしさを取り戻すきっかけを見つける場所」
そんな、やわらかな居場所でありたいと思っています。
「転職した方がいいのかな?」
「続けられる働き方ってあるのかな?」
「わたしに何ができるんだろう?」
その問いに、焦って答えを出す必要はありません。
答えが出なくても、考え続けることに意味があります。
そして、その道のりを一緒に考えられる仲間がいるだけで、心はずっと軽くなるはずです。
“せんせい、ちょっと休憩しよ。”
このブログが、あなたの休憩時間の片隅に、そっと寄り添えますように。
またいつでも、ここに帰ってきてくださいね。
最後に|あなたに合った記事から、少しずつ読み進めてみてください
このブログでは、毎日がんばるママ先生が「ちょっと休憩」しながら、自分にとっての働き方や生き方を見つけていけるように、いくつかのカテゴリに分けて記事を発信しています。
「今の自分に必要な情報から読んでみたい」
そんな気持ちに寄り添えるよう、それぞれのテーマごとにまとめています。
◆ 子育てと教員のリアル
日々の忙しさ、両立の大変さ、時間のやりくり…
「わかる!」が見つかるリアルな話をお届けします。
◆ 転職・働き方の選択肢
辞めたい…けど不安。そんな時に読んでほしい、
転職だけでなく「続ける」ための道も紹介します。
◆ お金と暮らしの不安を減らすヒント
生活費、退職金、扶養、非常勤…知っておくだけで安心できる、教員ママのためのお金の話。

